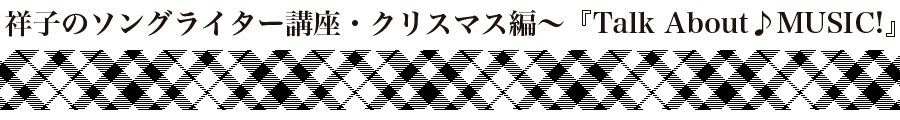第3回『超・個人的音楽史~その2~スティーヴ・ペリーと私』』
唐突ですが。。。私、スティーヴ・ペリーが好き過ぎて、いままでジャーニーについて一度も書いたことが無かったのです。
大人気グループだった80年代を過ぎると、彼らについてのニュースは殆ど日本に入って来なくなりました。90年代になって復帰作が一枚、ソロアルバムが一枚出たものの再び沈黙、正式な脱退もアナウンスされず、ソロアルバムの噂も来日の噂も聞かれず、気づけば声そっくりの後任ボーカリストが。。。
意味がわからないわ????
と、ここ何年かUSAのサイトやインタビュー記事を探しては読み漁り、浮かび上がってきたのはバンド内の確執と、スティーヴ・ペリー脱退の信じたくない、あまりに酷い真相でした。
いまここで詳しく触れるつもりはありませんが、'81年の新宿厚生年金会館、82年の武道館、83年の横浜文化体育館で素晴らしいコンサートを体験しているティーンエイジャーからのファンとして、想い出を汚されたような気持ちになったのは本当です。
もうひとつは。。。単純に好き過ぎて恥ずかしい、と言う乙女(当時。)ゴコロが呆れるくらいそのまま保存されているからなのです。
80年代中盤、ジャーニー=産業ロックの代表、という某大物評論家のネガティブ・キャンペーンが効を奏したおかげで、産業ロック=格好悪い=時代遅れという恐怖の図式が出来上がり、ジャーニーのジャ、の字を出したそばから自称・業界人からはフフン、と鼻で笑われる状況と言うのが本当に在ったのです。私がデビューした頃です。決して被害妄想で言ってるのではアリマセン。
某大物評論家、『ロック・オブ・エイジズ』を観たでしょうか?あの映画の一番のハイライトシーンで歌われたのが『ドント・ストップ・ビリーヴィン』だったことの意味は大きいです。30年経ってもあの曲は当然のように生きていたのです。格好悪くて時代遅れと言った奴等は全員反省してほしいものです。
思えば中2中3高1と、あたしの音楽人生は絶好調でした。アメリカのバンドが好き、ベストヒット・USAが大好き。中でもジャーニーは特別でした。黒髪、ロングヘアの中性的なリードシンガーの声と言ったら、一度聴いたら忘れられない響きだったのです。
澄みきったハイトーン・ヴォイスの中には何ともいえない哀愁と陰影があり、本国は勿論日本であんなに人気が出たのはその情緒的な声質に拠るところが凄く大きかったのではないでしょうか。
この世にこんなに私の理想どおりの王子様が居るなんて夢なのかしら??と思うくらい、エキゾチックで影のある目をしたスティーヴ・ペリーは魅力的でした。ジャーニーに加入してまだ2年、弱冠30歳の彼の笑顔や物腰にはシャイな初々しさが漂っていました。
その後、スターダムのプレッシャーからかツアーのストレスからか、若干の戸惑いを禁じ得ない外見の変化に「私の王子様伝説」は何度か危機を迎えたものの、それでもその声ほど私を夢中にさせ、我を忘れさせたものは在りませんでした。
あなたが歌うのをやめたとき、世界はひとつ光をうしなった。
と去年歌詞に書いたのは正直な気持ちです。歌はたのしい。ワクワクして胸がときめきます。解放されます。自由になります。
プロになったらそれは仕事です。お金がかかってます。掛かってると賭かってる、両方の意味があります。あなたは歌わなくなって、レコードの中にだけ居る人になった。
それが悲しいとか悔しいとか、そんな感慨はもうありません。あなたは歌い、たくさんの人を夢中にし、ある時歌うのをやめた。ただそれだけのことです。
レコードをかければ、CDをセットすればあなたの声が聴ける。永遠に20代から30代のままのあなたがそこに居る。それだけで十分なのです。
自分がこれからも歌うのか歌わないのか、そんなことはあまり重要じゃない。本当に重要なのは音楽です。
音楽活動じゃない、音楽です。それは似てるけどまったく一緒ではありません。
ジャーニー自体は今も存続しています。声そっくりのボーカリストを入れて。スティーヴ・ペリーの声だけにある陰影も、他の誰にも醸し出すことの出来ない情感も、それがどんなに彼らの曲を特別にしたか、多くの人の胸に焼きついて離れなくなったか。“産業”にとってはそんなことはどうでも良く、ただ同じキーを出してツアーを回れる歌い手が居れば良かったのです。
ねっ、思い入れと大好きを通り越して怒りが入ってきちゃう。だから一度も書けなかったんだ。
でも――と私は思います。あなたはもうすべてを赦しているでしょう。だからロックンロール・ホール・オブ・フェイムのセレモニーに顔を見せたのでしょう。変わらぬ黒髪のロングヘアが、笑顔が嬉しかったのです。
胸にのこるのはあの感動、音楽の圧倒的な力です。真似して買ったナイキの、赤にシルバーのラインのスニーカー、長い髪をなびかせて歌う姿、
コンサートのあと熱に浮かされたように新宿駅への道をたどった夜の、過ぎてゆく車のライトの眩しさ、ボーイフレンドがちょっと目をつぶってて、と首にかけてくれたJOURNEYのベンダント、
紺色の制服の自分、あなたのレコードに夢中だったたくさんの昼と夜、
人生のひとときにあなたが居て、私達に歌ってくれたこと。あなたがたしかにそこに居て、音楽は永遠だとおしえてくれたこと。